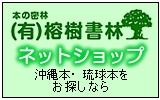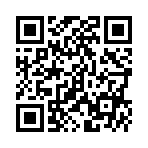2023年10月27日
『国立台湾大学図書館典蔵 琉歌大観』完結、4巻販売開始のお知らせ 及び既刊本価格変更のお知らせ
『国立台湾大学図書館典蔵 琉歌大観』4巻(最終巻)が沖縄に到着しました。
本日より販売開始いたします。
B5判、394頁、本体価格7000円(税込7700円)
~既刊本価格変更のお知らせ~
申し訳ございませんが、円安による仕入れ値upに伴い、
下記書籍8点の価格をそれぞれ本体価格7000円に変更致します。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
『国立台湾大学図書館典蔵 琉歌大観』1~3巻
『国立台湾大学図書館典蔵 琉球関係史料集成』1~5巻


本日より販売開始いたします。
B5判、394頁、本体価格7000円(税込7700円)
~既刊本価格変更のお知らせ~
申し訳ございませんが、円安による仕入れ値upに伴い、
下記書籍8点の価格をそれぞれ本体価格7000円に変更致します。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
『国立台湾大学図書館典蔵 琉歌大観』1~3巻
『国立台湾大学図書館典蔵 琉球関係史料集成』1~5巻


2023年10月19日
近日発売開始! 『校註 尚家本『喜安日記』』
森 威史 編著
校註 尚家本 喜安日記
琉球国尚寧王の駿府・江戸参府の年譜と史料
1609年(慶長14年)薩摩島津軍が琉球侵攻
琉球唯一の同時代史料を綿密に校訂・註記し、合せて「喜安日記」に関連する諸史料を収録
1609年(慶長14年)、島津三千の精強軍が琉球を襲い占領し、時の国王尚寧はとらえられ、薩摩に連行され、島津支配への屈服を強制され、起請文を書かされるとともに、駿府の徳川家康と会見し、更に江戸城では第二代将軍徳川秀忠と会見。その後、再び薩摩に戻り琉球に帰されることとなった。
この一連のできごとを記した琉球側の唯一の残存史料が「喜安日記」である。著者喜安は堺の人で、琉球の茶道の師として招かれ、尚寧王の側近となっていた人物であり、尚寧王が連行される際にも同道し、それらを詳細に記録していたのである。
従来「喜安日記」は伊波本と屋良本との二本が知られ、それらをもとにした読み下し本が一般には流布していた。那覇市史や日本国民生活史料集成のものがそれである。当社が「喜安日記」として刊行していたものも同種である。
2018年、琉球国王尚家の末えい尚衞(しょうまもる)氏から尚家文書が那覇市に寄贈されたが、その中にあった「喜安日記」を元に、従来のものと比較検討し改訂を加えたものに詳細な校註を施したものが本書である。いわば「喜安日記」の定本といっていいであろう。
又、「喜安日記」に出てくる諸事件に関連する史料を広く収集編纂して、計104点を収録し、著者による尚寧王の駿府での徳川家康との会見を詳しく解明した論考も収めた。
A5判、上製、凾入、358頁(含グラビア4頁・索引9頁)
定価8800円(本体8000円+税)
ISBN978-4-89805-240-2
目次
はじめに
凡例
校註 尚家本『喜安日記』
琉球国尚寧王の駿府・江戸参府の年譜と史料
収録史料 全104本
付載論考 慶長15年琉球国尚寧王の駿府登城
尚家本『喜安日記』索引
人名索引・地名索引・社寺索引
編著者プロフィール
森 威史(もり・たけし)
横浜に生る。国学院大学史学科卒、久能山東照宮博物館副館長他を経て、1983年静岡人類史研究所を創立。所長として活躍するも二〇〇九年退任。現在、静岡文化財研究所学術顧問。
校註 尚家本 喜安日記
琉球国尚寧王の駿府・江戸参府の年譜と史料
1609年(慶長14年)薩摩島津軍が琉球侵攻
琉球唯一の同時代史料を綿密に校訂・註記し、合せて「喜安日記」に関連する諸史料を収録
1609年(慶長14年)、島津三千の精強軍が琉球を襲い占領し、時の国王尚寧はとらえられ、薩摩に連行され、島津支配への屈服を強制され、起請文を書かされるとともに、駿府の徳川家康と会見し、更に江戸城では第二代将軍徳川秀忠と会見。その後、再び薩摩に戻り琉球に帰されることとなった。
この一連のできごとを記した琉球側の唯一の残存史料が「喜安日記」である。著者喜安は堺の人で、琉球の茶道の師として招かれ、尚寧王の側近となっていた人物であり、尚寧王が連行される際にも同道し、それらを詳細に記録していたのである。
従来「喜安日記」は伊波本と屋良本との二本が知られ、それらをもとにした読み下し本が一般には流布していた。那覇市史や日本国民生活史料集成のものがそれである。当社が「喜安日記」として刊行していたものも同種である。
2018年、琉球国王尚家の末えい尚衞(しょうまもる)氏から尚家文書が那覇市に寄贈されたが、その中にあった「喜安日記」を元に、従来のものと比較検討し改訂を加えたものに詳細な校註を施したものが本書である。いわば「喜安日記」の定本といっていいであろう。
又、「喜安日記」に出てくる諸事件に関連する史料を広く収集編纂して、計104点を収録し、著者による尚寧王の駿府での徳川家康との会見を詳しく解明した論考も収めた。
A5判、上製、凾入、358頁(含グラビア4頁・索引9頁)
定価8800円(本体8000円+税)
ISBN978-4-89805-240-2
目次
はじめに
凡例
校註 尚家本『喜安日記』
琉球国尚寧王の駿府・江戸参府の年譜と史料
収録史料 全104本
付載論考 慶長15年琉球国尚寧王の駿府登城
尚家本『喜安日記』索引
人名索引・地名索引・社寺索引
編著者プロフィール
森 威史(もり・たけし)
横浜に生る。国学院大学史学科卒、久能山東照宮博物館副館長他を経て、1983年静岡人類史研究所を創立。所長として活躍するも二〇〇九年退任。現在、静岡文化財研究所学術顧問。
2023年09月25日
本日発売開始!! 『聞書・中城人たちが見た沖縄戦 津覇にゆかりのある人々を中心に』 沖縄学術研究双書17

久志隆子・橋本拓大著
中城村津覇は沖縄戦では決して大きな戦場というわけではなかった。とはいえ集落には日本軍の陣地があり、集落民は陣地構築にかり出され、戦闘が始まると様々な形で否応なしにまきこまれていくこととなった。
戦争から既に七八年、記憶は薄れ様々な事件が忘れ去られてしまうことになりかねない状況の中で集落出身者であることを一つのテコとして、戦争体験者の記憶を聞書という形で引き出した成果が本書である。
戦争の記憶の多くは悲しみと苦痛を伴うがゆえに、これを封印してしまうことが少なくない。以前は話すことを了としなかった人でも時と共に新たな語りが始まる。以前には応じなかった人が重い口を開くとき、沖縄戦は更に新しい実相として姿をあらわしてくるのである。
本書は著者の修士論文作成の一環として二〇一七年から二〇二二年にかけて、集落の戦時経験者二〇余名からの聞き書きをもとに製作された。一部は方言のまま文字化されている。証言者は全て写真入りで登場し、地域の人々にとってはすこぶる臨場感のあるものとなっている。
市町村史編集が盛んな沖縄ではあるが、そこからもれ落ちた証言も少なくないはずである。本書が世代を超えた記憶の継承に役立ってくれれば嬉しい限りである。
A5判、並製、317頁
定価2970円(本体2700円+税)
目次(抄)
序にかえて
本書執筆の動機と研究の目的
先行する聞き書き実践や証言集等
第一章 中城村と同村字津覇における沖縄戦のあらまし
第二章 沖縄戦前夜の状況
第一節 学校生活
第二節 地域での生活
第三章 沖縄戦中の住民の行動
第一節 日本本土(熊本)へ疎開した人
第二節 沖縄本島北部へ疎開した人々
第三節 南部へ避難した人々
第四節 中城村(津覇・奥間)に留まった人々
第五節 捕虜になってから収容所での生活
第六節 従軍した看護要員、炊事婦、「学徒出陣」
第七節 外地・テニアンでの戦争体験との比較
第四章 戦後を生きる
第一節 沖縄戦終戦直後の生活
第二節 戦後にハウスメイドをしていた女性たちの座談会の記録
第三節 ハワイに連行された一兵士の家族の戦後の生活、ブラジルへの出移民
第五章 沖縄戦の体験を振り返った体験者 の考えや思い等
久志隆子
1955年 沖縄県中城村に生る
1980年 京都教育大学卒
中学校で国語教師を勤めた後
2021年 琉球大学大学院博士課程修了
橋本拓大
1966年 埼玉県深谷市生まれ
1984年 埼玉県立熊谷高校卒業
1989年 立教大学文学部史学科卒業
1989年 NHKに記者として入局
2023年 現在NHK国際放送局World News部所属
2023年09月25日
ジュンク堂書店古書コーナー移動のご案内
以前よりジュンク堂書店那覇店に古書を出品しておりましたが、今回のジュンク堂改装に伴い地下と2階に棚が分かれていたのが1階に全て移動しております。
場所はイタリアントマト側壁面、以前沖縄関係の文庫・新書が置かれていた棚になります。

場所はイタリアントマト側壁面、以前沖縄関係の文庫・新書が置かれていた棚になります。

2023年07月24日
2023年06月30日
只今発売中!! 沖縄文化への招待 ―歴史・伝統・日常生活の日本語と英語による概説―

宮城信夫著
本書は沖縄の歴史と文化、日常等を日本語と英語で概説したもので、他府県民のみならず沖縄県民や、琉球王国にルーツを持つ世界のウチナーンチュたちの沖縄への理解を深めるため、独断で選んだ幾つかのキーワードの概説を試みたものである。本書では日常生活の中で県民が話題にする項目を取り上げており、沖縄に興味を持つ読者の手引き書として学習に役立ててほしい。
A4判、246頁
目次(節は省く)
第1章 歴史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第2章 琉球から沖縄へ ・・・・・・・・・・・・・・・87
第3章 文化・史跡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102
第4章 沖縄県民の日常生活 ・・・・・・・・・・143
第5章 沖縄の貴重生物 ・・・・・・・・・・・・・・185
第6章 沖縄戦 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193
第7章 米軍統治時代 ・・・・・・・・・・・・・・・・207
第8章 日本(祖国)復帰 ・・・・・・・・・・・・223
第9章 沖縄から世界へ ・・・・・・・・・・・・・・・231
2023年06月16日
2023年05月12日
2023年05月12日
2023年03月22日
2023年03月20日
『境域の近世 慶長戦役後の琉球と薩摩』

上原兼善(岡山大学名誉教授)著
一六〇九年(慶長一四年)島津氏は三千の兵を琉球に送り、首里城をおとしいれ、国王尚寧を捕虜として薩摩につれ去った。以後、「琉球処分」に至るまで琉球は事実上島津家の支配におかれることとなり、このことは今日に至るまでいわゆる「沖縄問題」の根源として多くの人々の記憶の中に生きている。
著者は二〇〇九年に『島津氏の琉球侵略』を上梓し、琉球と薩摩がどの様にして慶長の役に至ったのかを明らかにし、好評を得た。
本書は、慶長の役の後、薩摩支配下の琉球と薩摩との関係史を掘り起し、いわゆる両属体制下にあって琉球側がいかにしてその主体性を維持する為に苦心し、王国としての存立を希求してきたのかを明らかにする。
慶長戦役後、国王尚寧は島津氏に引き立てられた上で徳川将軍と会見したが、これを契機として機会あるごとにいわゆる「江戸立ち」をすることになるが、この「江戸立ち」はその都度、薩摩藩の内情、琉球王府の内情、そして幕府の政治状況が複雑にからみあう、かけひきの場でもあった。それは日本薩摩―琉球の関係のみならず東アジアの政治情況とも連動するものであった。
本書では、それらの動きと関係史料を再吟味した上で新たな史料を読み解き、琉球―薩摩の関係史に新たな光を与えるものである。
前著『島津氏の琉球侵略』のいわば続編であると共に、「琉球処分」の前史でもある。
A5判、並製、232頁
定価2,970円(本体3,600円+税)

〈目次〉
はじめに
一 琉球使節の成立
二 東アジア世界の変動の中で
三 羽地朝秀の財政改革
四 「唐之首尾御使者」
五 宝永七年の琉球使節
六 正徳期の書翰問題
七 隠蔽と開示の狭間で
八 島津重豪と琉球使節
九 「琉球仮屋」から「琉球館」へ
一〇 輻輳する使者派遣儀礼
一一 窮迫する島津財政
一二 中城王子の御目見問題
一三 実現されない使者参府
一四 使者派遣制の変革
一五 「琉球処分」前夜の鹿児島藩(県)の動向
終章 琉球館の終焉
参考文献・史料
*著者紹介*
上原兼善
一九四四年、沖縄に生る。九州大学文学研究科博士課程中退、岡山大学名誉教授。研究の功績に対し第37回東恩納寛惇賞授賞。
著書に『鎖国と藩貿易』(一九八一)、『幕藩体制形成期の琉球支配』(二〇〇一)、『島津氏の琉球侵略』(二〇〇九)、『近世琉球貿易史の研究』(二〇一七、徳川賞/角川源義賞/日経・経済図書文化賞)
2023年03月20日
只今発売中!『琉球浄瑠璃 久志の若按司』

松山傳十郎著/茂木仁史解題
琉球王国は一八七九年(明治一二年)、明治政府による廃藩置県によって滅亡させられた。いわゆる「琉球処分」であった。明治政府の軍事力をバックに沖縄には多くの寄留商人や得体の知れない文士らが来琉し、琉球の日本化を推し進めた。しかしその中で琉球の歴史や文化を尊重し、これを紹介したり研究したりする人もいないではなかった。
松山傳十郎もその一人といえよう。松山のことはよくわかっていない。沖縄で新聞記者をしたり雑誌に記事を書いていたらしいが、彼の名を琉球・沖縄史にとどめているのは一冊の本の刊行である。その一冊こそ今回復刻出版することとなった
琉球浄瑠璃 内題・久志の若按司(明治二二年、いろは家)
である。B6判九二頁の小さな本である。この本は琉球に「組踊」と呼ばれる完成度の高い古典芸能があることを全国に知らしめることとなった。松山傳十郎が何故に『琉球浄瑠璃』というタイトルとしたかは定かではない。浄瑠璃に似ているとでも思ったのであろうか。
組踊は元々は一七一九年に琉球国王尚敬の冊封の為に来琉した冊封使一行(正使海宝・副使徐葆光)を歓待する為に首里城にて初めて演じられたもので、それゆえ組踊は首里の王族を中心とした上級士族の芸能として伝えられていたもので、その後徐々に地方に伝播し、琉球王国の崩壊で一気に花開き、一般市民の中に拡がっていったもので、従ってその台本も全て写本としてしか伝わっていなかった。
松山傳十郎はその中でも人気のあった「久志の若按司」を活字化し、『琉球浄瑠璃』として刊行したのである。
復刻にあたっては原本をそのまま影印で復元すると共に、今の人には読みにくいので文字の読解の参考を「しおり」として添付すると共に、国立劇場おきなわの調査養成課課長茂木仁史氏の詳細な解説を附した。

B6判、並製、132頁 限定三〇〇部
定価1,650円(本体1,500円+税)
2023年03月01日
只今発売中!! 琉球弧叢書№37 『首里城の舞台と踊衣裳』

茂木仁史・古波蔵ひろみ著/国立劇場おきなわ監修
本書は「御城舞台の研究」と「踊衣裳と結髪の研究」という二つの論文を収録している。いずれも、琉球国時代の組踊や琉球舞踊の姿を明らかにしようとする試みである。
「御城舞台」とは、琉球国王一世一代の「冊封」に際して首里城の御庭に作られた特設舞台のことである。一七一九年に初めて記録上に現われ、最後の琉球王・尚泰の冊封が行われた一八六六年まで、わずか五回しか姿を見せなかった幻の舞台である。その一五〇年ほどの間にも、芸能の変化に合わせて御城舞台も姿を変えるが、舞台と楽屋を橋掛りでつなぐという能舞台にも似た特殊な形は堅守された。この基本構造は琉球国の芸能の本質と通じ、変化した部分は琉球芸能の現在につながっている。
琉球芸能の「踊衣裳」といえば紅型衣裳に代表されるが、琉球国時代には異なる伝承があった。若衆の凛とした佇まいと色気を際立たせる「板締縮緬若衆衣裳」と、大人の女性の優美な気品を示す「琉縫薄衣裳」である。しかし、当時の衣裳はほとんど伝世されず、技術も廃れたことから幻の衣裳となっていた。本書ではこれまでの研究も踏まえつつ、琉球国の踊衣裳を具体的に示すよう目指したものである。また、結髪や髪飾りなどは近現代に変化したものもあるため、衣裳と一体になって装いを構成するものとして研究対象とした。
琉球国時代の芸能の実態については、明らかにされていないことも多い。今後の研究や公演に本書が寄与することを願うものである。(茂木仁史)
A5判、上製、296頁
定価(本体3,600円+税)
〈目次〉
Ⅰ 御城舞台の研究
はじめに
序章 芸能と舞台
第一部「御城舞台」の図像研究
第一章 一七一九年の御城舞台
第二章 一八三八年の御城舞台
第三章 一八六六年の御城舞台
第二部「御城舞台」の諸相
第四章 一八三八年の稽古と稽古場
第五章 躍が上演された場所
第六章 御膳進上と諸行事
第七章 舞台飾りと道具
第八章 観客と観客席
第九章 御城舞台の形状と寸法
おわりに
Ⅱ 踊衣裳と結髪の研究
はじめに
第一部踊衣裳の研究
第一章老人踊
第二章若衆踊
第三章女踊
第二部結髪の研究
第四章欹髻―老人・成人男子の髪型
第五章丸結の研究
第六章垂髪とかつら髪
おわりに
*著者紹介*
茂木仁史
沖縄県立芸術大学大学院芸術文化学研究科(博士後期課程)修了、芸術学博士
国立劇場おきなわ調査養成課課長
沖縄県立芸術大学芸術文化研究所 共同研究員
古波蔵ひろみ
琉球大学大学院人文社会科学研究科(博士後期課程)修了、学術博士
沖縄県立芸術大学芸術文化研究所共同研究員
2023年01月12日
1/14(土)~2/28(火)まで 第6回 ジュンク堂 新春古書展のご案内
明後日14(土)~2/28(火)までジュンク堂書店那覇店に於いて『第6回 ジュンク堂 新春古書展』を開催致します。当初の予定では、2/12(日)までとなっておりましたが、急きょ2/28(火)まで開催の延長が決定致しました!! チラシ上では、2/12(日)となっておりますが、間違いですのでご注意ください。毎年恒例の古書展では、沖縄(琉球)の歴史や文学をはじめとする稀覯本や絶版本等その他、普段新刊書店では観ることの出来ない古書、古本を多数出品販売致します。古書(古本)を専門に扱うお店ならではの品揃えの中から、掘り出し物の1冊に巡り会えるチャンスです。昨年、全沖縄古書籍商業組合へ入会致しました新組合員を含め、今古書展は、これまでの中で過去最大の出品店舗数及び出品規模数となり、これまでになく見応え十分です。新組合員にとっては、初の古書展参加となり、皆張り切って準備をしております!! 今古書展注目商品は、1949年刊『徳田球一大演説記念アルバム』をはじめ、キリスト教関係書籍や人文・アート、絵本・サブカル、医療関係書籍等々ジャンル問わず多数ございます。ただし、売り切れ次第、終了となります。ご希望のお客様は、お早めにどうぞ。また期間中、下記の通りイベントを4つ開催致します。(コロナ感染状況他諸事情により急きょ、中止・日程変更の可能性有、その場合は改めて当ブログにてお知らせ致します。)いずれもイベントの観覧は無料です。お近くへお越しの際は、お気軽にお立ち寄りいただけますと幸いです。参加店一同、皆様のご来店、ご来場をお待ちしております。新春古書展に関するお問い合わせは、ジュンク堂書店那覇店(098-860-7175)または各店(参加古書店)まで。
1/14(土)18時~
ボーダーインク『泡盛をめぐる沖縄の酒文化史』刊行記念
ほろ酔い酒談議―酒と本の日々
萩尾俊章氏 × 豊見山和行氏
1/22(日)17時~
榕樹書林『組踊の歴史と研究』刊行記念
芸能の島・沖縄
鈴木耕太氏 × ゲストX氏
1/29(日)17時~
琉球怪談古典編 朗読と解説による逆立ち幽霊他
神崎英敏氏(朗読) × 小原猛氏(解説)
2/11(土祝)13時~
新入組合員井戸端座談 × FM那覇
ライフセンター ビブロス堂
ブックパーラー 砂辺書架
波止場書房
Second hand-Shop 金ちゃん
本と商い ある日、


1/14(土)18時~
ボーダーインク『泡盛をめぐる沖縄の酒文化史』刊行記念
ほろ酔い酒談議―酒と本の日々
萩尾俊章氏 × 豊見山和行氏
1/22(日)17時~
榕樹書林『組踊の歴史と研究』刊行記念
芸能の島・沖縄
鈴木耕太氏 × ゲストX氏
1/29(日)17時~
琉球怪談古典編 朗読と解説による逆立ち幽霊他
神崎英敏氏(朗読) × 小原猛氏(解説)
2/11(土祝)13時~
新入組合員井戸端座談 × FM那覇
ライフセンター ビブロス堂
ブックパーラー 砂辺書架
波止場書房
Second hand-Shop 金ちゃん
本と商い ある日、


2023年01月11日
只今、発売中!! 琉球弧叢書36 組踊の歴史と研究

鈴木耕太著(沖縄県立芸術大学准教授)
本書は組踊研究の若手第一人者として活躍する鈴木耕太氏による組踊研究の新しい枠組みと視座をもとにした注目すべき論稿から成り立っている。
組踊は中国皇帝の使者冊封使を迎え、歓待する為に、玉城朝薫によって日本の能や歌舞浄瑠璃、更には中国演劇などからも着想を取り入れて作られ、1719年、冊封使徐葆光(じょほうこう)を迎えて初演されたのを契機とし、国家儀礼の一環として発展してきた。琉球処分によって組踊を担ってきた上級士族が地方に分散することによって全琉球文化圏へと拡散し、庶民の芸能となり多くの人々に親しまれている。
本書ではその歴史を詳細に調べ上げると共に、上演台本の校合によって組踊の伝播と演出の変化等を明らかにする。
組踊研究が日本の芸能史研究あるいは中国芸能の琉球への導入等を踏まえ、その特質を捉え直し、これからの研究の礎石となるであろう。
A5判、上製、422頁
定価(5,800円+税)
〈目次〉(抄)
序にかえて― 組踊のいま
第一章 組踊の誕生―玉城朝薫と組踊創作の背景―
第一節 組踊の作者:玉城朝薫と尚敬王
第二節 「組踊誕生」試論
第二章 組踊の歴史―上演および研究の歴史
第一節 近世琉球期(組踊誕生から琉球処分まで)
第二節 明治・大正・昭和初期(1879年~1945年)
第三節 戦後~復帰まで(1945年~1972年)
第四節 組踊研究史
第三章 組踊本の校合と研究
第一節 尚家本組踊集の校合と結果―「執心鐘入」を中心に
第二節 常套句(じょうとうく)の使用について考える―「拝み留やへて」論
第三節 組踊と「季節」
第四節 組踊における役名について
第五節 近世における組踊をめぐって
―上演作品・舞台・小道具、そして近代への伝承
第六節 沖永良部島と組踊―道の島と琉球の文化伝承に関する一考察
第四章 資料編
一 組踊校訂本の試み―「執心鐘入」を題材として
二 組踊異表題一覧
三 組踊関係年表《抄》(近代沖縄~復帰編)
おわりに
*著者略歴*
鈴木 耕太(すずき こうた)
沖縄県読谷村に生まれる。
沖縄国際大学国文科卒業、琉球大学大学院(修士)
沖縄県立芸術大学後期博士課程修了、芸術学博士
2016年より沖縄県立芸術大学芸術文化研究所に勤務
共著に『沖縄芸能のダイナミズム』『琉球・沖縄芸能史年表』がある。
2023年01月06日
*新年のご挨拶*

あけましておめでとうございます。
旧年中は、格別のお引き立てを賜りまして、厚く御礼申し上げます。
本年も、より一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
旧年中は、格別のお引き立てを賜りまして、厚く御礼申し上げます。
本年も、より一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
Posted by 沖縄本といえば榕樹書林 at
14:17
│Comments(0)
2022年12月23日
*年末年始休業のお知らせ*
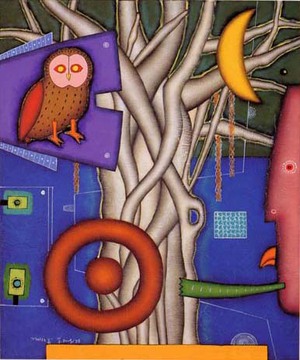
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、年末年始の休業を下記の通りご案内させていただきます。
休業期間 2022年12月29日(木) ~ 2023年1月5日(木)
上記期間は、ネットショップの対応業務も休止致します。
尚、ご注文およびメールでのお問い合わせは通常通り受け付けておりますが、
発送および返信は1月6日(金)以降となります。
何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら、年末年始の休業を下記の通りご案内させていただきます。
休業期間 2022年12月29日(木) ~ 2023年1月5日(木)
上記期間は、ネットショップの対応業務も休止致します。
尚、ご注文およびメールでのお問い合わせは通常通り受け付けておりますが、
発送および返信は1月6日(金)以降となります。
何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
Posted by 沖縄本といえば榕樹書林 at
18:55
│Comments(0)