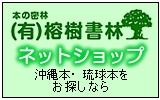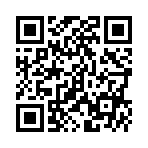2025年03月24日
只今発売中! 『はじみらなうちなーぐち』

本書は沖縄の精神世界の基礎である「うちなーぐち」(沖縄語)を楽しく学ぶ為の絶好の書である。
本書における語句の解説は簡明であり、著者の三〇年余にわたる「うちなーぐち」の研究成果に基づくものである。それは、およそ二五年に及ぶ沖縄語の献身的な普及活動に裏付けされているものであり、「うちなーぐち」という精神遺産に対するほとばしる情熱がいたるところで感じられよう。
本書の特典の一つは信頼できる仮名表記なので、初心者でも安心して学ぶことができることにある。二〇〇〇年に著者が沖縄語普及協議会設立を呼びかけ、同会の事務局長をしていた当時から、沖縄語の仮名表記法を提唱してきたが、先に刊行された『うちなーぐち活用辞典』(二〇二一年、国立国語研究所発行)の巻末では表記の心得としてまとめられており、本書はその成果を誰にでもわかる様に簡明にしたものである。
本書の巻末では、第一課から第十五課までの会話を仮名と漢字で表記する試みも提示されている。
「うちなーぐち」の学習帳として本書を大いに愛用し、沖縄の心に少しでも触れてもらいたい。
宮良 信詳 著 並製・110頁・B5判 定価1870(本体1700)円
ISBN978-4-89805-258-7
〈内容〉
うちなーぐち⑴ ~ ⒂
てぃーち⑴~とーいちち⒂
■参考文献
付録1 沖縄語の平仮名一覧表
付録2 仮名と漢字表記
表記と練習問題の解答
■研究業績一覧
☆解題ごとに練習問題あり
ご購入は弊社ネットショップ(https://gajumarubook.jp/?pid=185575641)
又は日本の古本屋(https://www.kosho.or.jp/abouts/?id=52000090)
よりお願いいたします。
2025年01月01日
新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。弊社の公式ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。
昨年は年明け早々店舗移転に奔走し、皆様のご支持をいただきながら事業を再開することができました。心より感謝申し上げます。
まだまだ移転後の整理がつかない状況ではございますが、どうぞ本年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
榕樹書林 武石 和実

弊社ネットショップよりご購入いただけます。※在庫僅少
https://gajumarubook.jp/?pid=164736538
付記
六年ぶりに新しい出版目録を発行致しました。ご希望の方には進呈致します。
弊社店頭及びジュンク堂書店那覇店にて配布中です。
2024年12月31日
*年末年始休業のお知らせ*
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、年末年始の休業を下記の通りご案内させていただきます。
休業期間 2024年12月30日(土) ~ 2025年1月5日(日)
上記期間は、ネットショップの対応業務も休止致します。
尚、ご注文およびメールでのお問い合わせは通常通り受け付けておりますが、
発送および返信は1月6日(月)以降となります。
何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら、年末年始の休業を下記の通りご案内させていただきます。
休業期間 2024年12月30日(土) ~ 2025年1月5日(日)
上記期間は、ネットショップの対応業務も休止致します。
尚、ご注文およびメールでのお問い合わせは通常通り受け付けておりますが、
発送および返信は1月6日(月)以降となります。
何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
Posted by 沖縄本といえば榕樹書林 at
15:32
│Comments(0)
2024年12月31日
只今発売中! 『柳田國男の民俗学と沖縄』
琉球弧叢書最新刊!
25年1月11日(日)、ジュンク堂にて出版記念トークイベント開催!
また、1月26日(日)には日本民俗学会談話会開催予定です。
日本民俗学会談話会詳細
1月26日(日)13:30~17:30 東京・國學院大學、ハイブリッド開催
「柳田國男の民俗学と沖縄―比較研究法の再評価―」
報告者:赤嶺政信
コメンテーター:澤井真代・島村恭則
コーディネーター:島村恭則
ご来場、ご参加お待ちしております。

柳田國男によって始められた日本民俗学にとって沖縄は様々な側面で 議論の中心の一つであった。沖縄民俗学は柳田國男あってのものであっ たし、又、民俗学研究の中で沖縄ははずすことのできないファクターであった。
本書は沖縄民俗の研究史と自身の 関わりをふまえつつ、研究方法論を めぐる論争の中で民俗学の様々な課題にどう対峙していくのか、又、それをふまえての研究をどう維持し進 めていくのかについて「比較研究法」 という立場に依りつつ問題を探っていく。
そしてこの方法論、つまりは柳田國男の積極的再評価の立場に立って、沖縄の行事、祭祀、シャーマニズム、婚姻習俗、葬制、建築儀礼、キジムナー等を解析していく。
著者の研究を総括した畢生の論文集。
赤嶺 政信著 上製本・357頁・A5判 定価7,700(本体7,000)円
ISBN978-4-89805-255-6
目次(秒)
序論
第一部 柳田國男の民俗学と沖縄
1 沖縄における民俗研究の歩み
2 柳田國男の民俗学と沖縄
3 南島から柳田國男を読む ―祖霊信仰論に焦点を当てて―
4 民俗と政治権力
第二部 比較研究法の実践
1 古琉球の盆行事をめぐって
2 三月三日孝
3 「をなり神の島」の男性神役
4 沖縄の祭祀とシャーマニズム ―宮古の事例を中心に―
5 沖縄の講をめぐって
6 沖縄の婚姻
(1)沖級の婚姻習俗をめぐって
(2)久高島の「逃走婚」とイザイホウ
7 食物から見た沖縄の葬儀
8 屋敷と門
9 沖縄の家の神をめぐって
(1)トゥハシリ考
(2)宮古の家の神
(3)八重山の家の神と建築儀礼
(4)建築儀礼に見える樹木霊に対する対処の仕方
ご購入は弊社ネットショップ https://gajumarubook.jp/?pid=183415096
又は日本の古本屋 https://www.kosho.or.jp/products/list.php?mode=search_newitem&baseinfo_id=52000090
にてお願い致します。
25年1月11日(日)、ジュンク堂にて出版記念トークイベント開催!
また、1月26日(日)には日本民俗学会談話会開催予定です。
日本民俗学会談話会詳細
1月26日(日)13:30~17:30 東京・國學院大學、ハイブリッド開催
「柳田國男の民俗学と沖縄―比較研究法の再評価―」
報告者:赤嶺政信
コメンテーター:澤井真代・島村恭則
コーディネーター:島村恭則
ご来場、ご参加お待ちしております。

柳田國男によって始められた日本民俗学にとって沖縄は様々な側面で 議論の中心の一つであった。沖縄民俗学は柳田國男あってのものであっ たし、又、民俗学研究の中で沖縄ははずすことのできないファクターであった。
本書は沖縄民俗の研究史と自身の 関わりをふまえつつ、研究方法論を めぐる論争の中で民俗学の様々な課題にどう対峙していくのか、又、それをふまえての研究をどう維持し進 めていくのかについて「比較研究法」 という立場に依りつつ問題を探っていく。
そしてこの方法論、つまりは柳田國男の積極的再評価の立場に立って、沖縄の行事、祭祀、シャーマニズム、婚姻習俗、葬制、建築儀礼、キジムナー等を解析していく。
著者の研究を総括した畢生の論文集。
赤嶺 政信著 上製本・357頁・A5判 定価7,700(本体7,000)円
ISBN978-4-89805-255-6
目次(秒)
序論
第一部 柳田國男の民俗学と沖縄
1 沖縄における民俗研究の歩み
2 柳田國男の民俗学と沖縄
3 南島から柳田國男を読む ―祖霊信仰論に焦点を当てて―
4 民俗と政治権力
第二部 比較研究法の実践
1 古琉球の盆行事をめぐって
2 三月三日孝
3 「をなり神の島」の男性神役
4 沖縄の祭祀とシャーマニズム ―宮古の事例を中心に―
5 沖縄の講をめぐって
6 沖縄の婚姻
(1)沖級の婚姻習俗をめぐって
(2)久高島の「逃走婚」とイザイホウ
7 食物から見た沖縄の葬儀
8 屋敷と門
9 沖縄の家の神をめぐって
(1)トゥハシリ考
(2)宮古の家の神
(3)八重山の家の神と建築儀礼
(4)建築儀礼に見える樹木霊に対する対処の仕方
ご購入は弊社ネットショップ https://gajumarubook.jp/?pid=183415096
又は日本の古本屋 https://www.kosho.or.jp/products/list.php?mode=search_newitem&baseinfo_id=52000090
にてお願い致します。
2024年12月31日
第8回 ジュンク堂新春古書展 開催のお知らせ

毎年恒例となりつつあります、ジュンク堂那覇店での新春古書展、開催が決定致しました。
期日は25年1月11日(土)~2月11日(火・祝)までとなっております。
県内12業者が参加致します。
期間中には関連イベントも開催予定です。
1/12(日) 15:00~ 『柳田國男の民俗学と沖縄』出版記念トークイベント
赤嶺政信(著者:琉球大学名誉教授)×平良次子(対馬丸記念館館長)
1/25(土) 15:00~ 絵本読み聞かせ講演会 子どもを育む絵本読み聞かせパワー
ビブロス堂店長 中村信義(NPO法人「絵本で子育て」センター認定絵本講師)
2/2 (日) 15:00~ 市場のモノガタリ
オーガニックゆうき(小説家)×宇田智子(市場の古本屋うらら店主)
司会:新城和博(ボーダーインク編集長)
三件とも会場は地下一階イベント会場となります。
また、今回トークイベント開催の琉球弧叢書最新刊『柳田國男の民俗学と沖縄』に関連し、
柳田國男関連書籍、原稿を出品致します。是非足をお運びくださいませ。

※データ量の制限の為ブログでは文字がぼやけてしまいます。申し訳ございません。
出品妙は参加古書店等で配布中です。
電子データでの送付も可能ですので、ご希望の場合はgajumaru@chive.ocn.ne.jp宛てにご連絡くださいませ。
2024年12月31日
只今発売中! 『古琉球を歩く 碑文散策考』

琉球沖縄の歴史を探ろうとすると残されている史料の少なさに愕然とする。元々なかったという訳ではない。一六〇九年の薩摩の琉球侵略によってそれ以前の史料の多くが奪い取られた。一八七九年(明治十二年)の琉球処分によって明治政府に奪われた史料はその多くが関東大震災によって消失した。残った数少ない史料も沖縄戦によって焼き尽くされたのである。
にもかかわらず石の文化が発達していた琉球には多くの石碑が残り、古い琉球の歴史と文化を今に伝えている。とはいってもそのほとんどは難解な漢文で記されており、一般の人には近づきがたいものがある。
著者は多くの金石文の中から古琉球期(一六〇九年以前)の二十六点を選び出し、その場所を案内し、その碑文の伝える内容を紹介するとともに、深い考察を加え、いまだ幻の中にある古琉球の社会と文化の謎にいどんだのが本書である。
本書を片手に、首里の街や浦添城周辺などを散策しながら、古琉球期の琉球王国に想いをめぐらして欲しい。
諸見 友重著 並製・246頁・A5判 定価2,970(本体2,700)円
ISBN978-4-89805-249-5
目 次
1 安国山樹華木之記
2 大安禅寺碑記
3 千仏霊閣碑記
4 旧首里城銅鐘/万国津梁の鐘
5 萬歳嶺記
6 官松嶺記
7 圓覺禅寺記/荒神堂之南之碑文
8 國王頌徳碑/荒神堂之北之碑文
9 サシカエシ松尾ノ碑文
10円覺寺松尾之碑文
11たまおどんのひのもん
12百浦添之欄干之銘
13そのひやふの御嶽の額の字
14眞珠湊碑文(石門の西のひのもん)
15国王頌徳碑/石門之東之碑文
16王舅達魯加禰國柱大人壽蔵之銘
17崇元寺下馬碑
18一翁寧公之碑
19国王頌徳碑/かたのはなの碑
20新築石墻記/添継御門之北之碑文
21新築石墻記/ 添継御門の南のひのもん
22やらさもりくすくの碑
23君誇之欄干之記
24広徳寺浦添親方塚碑
25浦添城の前の碑文
26極楽山の碑文
ご購入は弊社ネットショップ(https://gajumarubook.jp/?pid=183415297)
又は日本の古本屋(https://www.kosho.or.jp/products/list.php?mode=search_newitem&baseinfo_id=52000090)
よりお願い致します。
2024年12月31日
只今発売中! 『ペリー提督日本遠征書簡集―上海・香港・琉球・江戸湾・小笠原・箱館―』

1853 年、江戸湾にあらわれたペリー艦隊[黒船]は徳川幕府を根底からゆるがし、明治維新へと続く日本の近代化の狼火となるものであった。
ペリーの日本遠征については1854 年に『日本遠征記』(全3巻)が公刊され、それに付随する幾つもの書物が世に出ており、その主なものは日本語に訳されているので事の経緯はほぼ明らかになっている。『ペリー提督日本遠征記』は大変高い評価を得ているが、完訳本は1997 年に栄光教育出版社刊行のものまで待たなければならなかった。
関連する周辺資料の中で残された基本資料として知られていながら未訳であったのが、本書『米国上院議会への公式書簡報告書』であり、『遠征記』にも一部引用されているが、ペリー艦隊の東アジア遠征の目的やその意図について隠すことなく報告していること、そしてアメリカ側内部対立なども明らかにされていることが注目される。
従来の日本遠征をめぐる日本の議論では江戸湾の出来事とそれへの幕府の対応にのみ終始し、前後5回も訪れた琉球のことや小笠原諸島、箱館のことなどは軽く扱われているが、本書を読めばそのような対応ではペリー遠征について正しい把握はできないであろう。
本報告書はペリーの黒船をどうとらえるのか、という問いに新しい答えを引き出す大きな鍵となるものである。
梓澤 登訳 ティネッロ・マルコ解説 限定300部
並製・360頁・A5判 定価4,950(本体4,500)円 2024年刊行
ISBN978-4-89805-250-1
ご購入は弊社ネットショップ(https://gajumarubook.jp/?pid=183546524)
又は日本の古本屋(https://www.kosho.or.jp/products/list.php?mode=search_newitem&baseinfo_id=52000090)
よりお願いいたします。
2024年12月31日
只今発売中! 『牧志恩河一件』

琉球王国末期(幕末期)来琉した欧米艦船の交渉通事として非凡な才能を発揮した牧志朝忠は、その上司恩河朝恒、小禄良忠とともにとらわれの身となり、その才を高く評価した薩摩の介入で釈放され、鹿児島に渡る途中、海中に身を投じた。この疑獄事件は不明な点が多々あり、琉球史の大きな謎の一つとされてきた。
本書は「琉球三罷録」はもとより、伊江文書を読み解き、その事実関係をつきつめていく。
薩摩のお家騒動、琉球王府内の勢力争い、黒舩の脅威といった中で、いわば開明派と目される牧志恩河らへの厳しい取り調べの背景にあるものを浮かび上がらせていく。
関連資料も多数収録した決定版です。
金城正篤著 並製・318頁・A5判 2024年刊行 定価3,300(本体3,000)円
ISBN978-4-89805-256-3
目 次(抄)
序にかえて
一 牧志・恩河事件―なぜ「牧志・恩河」か―
二 「牧志・恩河事件」関係記録について
三 牧志・恩河事件について
四 伊江文書
牧志・恩河事件の記録について
五 牧志朝忠伝 二題
補論 牧志・恩河事件の背景
付録
一 置県後の士族の動向
――秩禄処分と士族授産
1 ひきのばされた「秩禄処分」
2 無禄士族と士族授産
3 「秩禄処分」とその特質
二 沖縄歴史論稿
1 伊波普猷と沖縄研究
2 沖縄研究の歴史と思想
三 書評
1 西里喜行著『清末中琉日関係史の研究』
2 海音寺潮五郎著『鶯の歌』朝日新聞社
ご購入は弊社ネットショップ(https://gajumarubook.jp/?pid=184054826)
又は日本の古本屋(https://www.kosho.or.jp/products/list.php?mode=search_newitem&baseinfo_id=52000090)
よりお願い致します。
2024年12月31日
只今発売中!! 『芭蕉布物語 新装改版』
大変長らくお待たせ致しました。
在庫を切らしておりました『芭蕉布物語』ですが、新装版にて再版いたしました。
お買い求めは弊社ネットショップ(https://gajumarubook.jp/?pid=182565136)
又は
日本の古本屋(https://www.kosho.or.jp/products/list.php?mode=search_newitem&baseinfo_id=52000090)
にてお願い致します。

柳 宗悦著、松井 健解題
柳宗悦とその同人一行は、昭和13年から15年にかけて4回にわたって来琉し、琉球における民藝の美を求めて各地を踏査した。その成果は幾つもの書籍として発表され、琉球の文化や伝統工藝を広く世に知らしめることとなった。『琉球の陶器』『琉球の文化』『琉球の織物』『琉球の型附』などである。『芭蕉布物語』もその中の一冊で、昭和17年に私家版、限定225部として刊行された、B5変型の漆染め和紙装の美しい本である。本書の奥附にはこう記されている。猥(みだり)に復刻すべきに非ず。こういうこともあって本書は全集等は別として復刻・再版されることもなく今日に至っている。しかし、『芭蕉布物語』が沖縄の戦後の伝統工芸、とりわけ芭蕉布の復興に果した役割は極めて大きいものがある。1974年に人間国宝に指定された喜如嘉の芭蕉布の平良敏子さんは、『芭蕉布物語』を読むことによって故郷の織物の美を再認識し、復興への決意を固めたという。戦後の荒廃の中での苦闘を支えたのは、柳宗悦による芭蕉布への賛歌だったのである。
本書の復刻・再版にあたっては原著のイメージを出来るだけ損なうことのないよう、印刷から紙、表紙に至るまで細かな配慮をした。解題は、この間、柳宗悦と民藝運動に関して、積極的に論を展開している松井健(東京大学名誉教授)先生にお願いし、ほぼ本文と同分量の濃密なものとなった。老齢化や過疎化、文化意識の変化等で伝統工藝はどこでも大きな危機にある。本書はその様な危機を乗り越えていくことへのエールとなろう。芭蕉布の美しさを再認識し、いつまでも残していく為に・・・。
並製本、B5変形版、124頁、内グラビア8頁 定価(本体2,000円+税)
2024年新装再版。
〈目次〉
前書(まえがき)/芭蕉布(ばしょうふ)/芭蕉糸(ばしょういと)/糸績(いとうみ)/
糸括(いとくくり)/糸染(いとぞめ)/桛巻(かせまき)/絣柄(かすりがら)/
機織(はたおり)/絣味(かすりあじ)/芭蕉着(ばしょうぎ)/夏衣(なつぎぬ)/
織手(おりて)/後書(あとがき)
〈目次〉 芭蕉布物語 解題
一、『芭蕉布物語』の位置
二、『芭蕉布物語』が語ること
三、 近代批判としての『芭蕉布物語』
四、『芭蕉布物語』爾後
註
※『私家版 芭蕉布物語』1点販売中!※
日本の古本屋にて購入いただけます。店頭受け取りご希望の場合も日本の古本屋にて御注文くださいませ。
https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=537709168

在庫を切らしておりました『芭蕉布物語』ですが、新装版にて再版いたしました。
お買い求めは弊社ネットショップ(https://gajumarubook.jp/?pid=182565136)
又は
日本の古本屋(https://www.kosho.or.jp/products/list.php?mode=search_newitem&baseinfo_id=52000090)
にてお願い致します。

柳 宗悦著、松井 健解題
柳宗悦とその同人一行は、昭和13年から15年にかけて4回にわたって来琉し、琉球における民藝の美を求めて各地を踏査した。その成果は幾つもの書籍として発表され、琉球の文化や伝統工藝を広く世に知らしめることとなった。『琉球の陶器』『琉球の文化』『琉球の織物』『琉球の型附』などである。『芭蕉布物語』もその中の一冊で、昭和17年に私家版、限定225部として刊行された、B5変型の漆染め和紙装の美しい本である。本書の奥附にはこう記されている。猥(みだり)に復刻すべきに非ず。こういうこともあって本書は全集等は別として復刻・再版されることもなく今日に至っている。しかし、『芭蕉布物語』が沖縄の戦後の伝統工芸、とりわけ芭蕉布の復興に果した役割は極めて大きいものがある。1974年に人間国宝に指定された喜如嘉の芭蕉布の平良敏子さんは、『芭蕉布物語』を読むことによって故郷の織物の美を再認識し、復興への決意を固めたという。戦後の荒廃の中での苦闘を支えたのは、柳宗悦による芭蕉布への賛歌だったのである。
本書の復刻・再版にあたっては原著のイメージを出来るだけ損なうことのないよう、印刷から紙、表紙に至るまで細かな配慮をした。解題は、この間、柳宗悦と民藝運動に関して、積極的に論を展開している松井健(東京大学名誉教授)先生にお願いし、ほぼ本文と同分量の濃密なものとなった。老齢化や過疎化、文化意識の変化等で伝統工藝はどこでも大きな危機にある。本書はその様な危機を乗り越えていくことへのエールとなろう。芭蕉布の美しさを再認識し、いつまでも残していく為に・・・。
並製本、B5変形版、124頁、内グラビア8頁 定価(本体2,000円+税)
2024年新装再版。
〈目次〉
前書(まえがき)/芭蕉布(ばしょうふ)/芭蕉糸(ばしょういと)/糸績(いとうみ)/
糸括(いとくくり)/糸染(いとぞめ)/桛巻(かせまき)/絣柄(かすりがら)/
機織(はたおり)/絣味(かすりあじ)/芭蕉着(ばしょうぎ)/夏衣(なつぎぬ)/
織手(おりて)/後書(あとがき)
〈目次〉 芭蕉布物語 解題
一、『芭蕉布物語』の位置
二、『芭蕉布物語』が語ること
三、 近代批判としての『芭蕉布物語』
四、『芭蕉布物語』爾後
註
※『私家版 芭蕉布物語』1点販売中!※
日本の古本屋にて購入いただけます。店頭受け取りご希望の場合も日本の古本屋にて御注文くださいませ。
https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=537709168

2024年08月15日
原田禹雄先生追悼文、琉球新報(08.15)に掲載

8月13日の琉球新報に原田禹雄先生追悼文が掲載されました。
筆者の又吉靜枝先生は琉球古典舞踊の第一人者であり、冊封使を迎えての琉球舞踊の復元に尽力された方です。
その際、原田禹雄訳注の『徐葆光 中山伝信録』を活用、原田先生直々の助言を受けられました。
記事全文は下記URLよりお願い致します。
https://ryukyushimpo.jp/news/obituary/entry-3365801.html
2024年07月29日
原田禹雄先生訃報のお知らせ

原田禹雄先生 追悼
当社の主要な出版物である『冊封琉球使録集成』の訳註者である原田禹雄(はらだのぶお)先生の訃報を受けました。4月28日、96歳で天寿を全うしたとの事です。謹んで哀悼の意を表します。
当社の出版活動は1991年の『空手道大観』から始まるが、その中核を担ったのは原田先生の訳注による『冊封琉球使録集成』(全11巻)であり、そこから派生した『琉球神道記』『質問本草』『琉球国旧記』『明代琉球資料集成』、そして先生の著作5冊を含む『琉球弧叢書』であった。
『冊封使録』は琉球中国関係史研究の基礎文献でありながらあまり活用されてこなかったが、先生の訳注本の刊行によって広く読まれ用いられるようになり、2016年の「東アジア出版文化賞」、2018年の「岩瀬弥助記念書物文化賞」の受賞は名こそあげられてはいないものの、実質としては『冊封琉球使録集成』の出版に対するものであった。
当社から刊行された原田先生の本は『冊封琉球使録集成』が11冊、『琉球弧叢書』が5冊、その他が7冊。全部で計23冊にのぼる。軽く読める内容の23冊ではない。難解故に誰も手をつけなかったものを現代語に訳し、詳細な註を加えた先生の本は、一般の市民の誰でもが冊封使録の世界に入っていけるようにしたという点で画期的なものであった。歴史研究者はもとより芸能史研究、食文化等ひろく活用されるようになった。学位論文でも冊封使録が取り上げられるようになり、琉球史研究の裾野を広げるのに大きく寄与したものと確信している。
先生の仕事は今後に続く人々を励まし続けるだろう。私共も又、これまでの足跡を大切にし、先生の仕事を最大限に高めていく為に努力していく事を誓いたい。
改めて先生の御冥福を心よりお祈り申し上げます。
2024年7月29日
榕樹書林 武石和実
榕樹書林 武石和実
先日公開致しました追悼文において一番重要な原田先生の命日を誤って4月26と記しておりましたが、正しくは4月28日となります。
大変申し訳ございません。
改めて原田先生の御逝去に哀悼の意を示したいと思います。
2024年8月8日 記事訂正
2024年02月27日
店舗移転のお知らせ
Twitterでは告知済みですが、ブログの存在を失念しておりました。
この度、移転先が無事定まりましたので、2/29をもって、現在の店舗での営業を終了致します。
新店舗での営業は4/1、店舗営業時間が12時からを予定しております。
また、開店セールを行います。期間は4/1~5/31までとなります。
古書のみ2割引にて販売致します。ご来店お待ちしております。
なお、現在地での事務所としての営業は3/14までを予定しております。
3/14までは納品、発注等は今現在の住所、連絡先へお願い致します。
3/15からは電話番号、FAX番号も変更致しますので、ご注意くださいませ。
新店舗連絡先
〒901-2215 沖縄県宜野湾市真栄原3-8-3 大光ビルⅢ-203
TEL:098-943-7991 FAX :098-943-7274
店舗営業時間 12:00~19:00
定休日:日曜・祝祭日


この度、移転先が無事定まりましたので、2/29をもって、現在の店舗での営業を終了致します。
新店舗での営業は4/1、店舗営業時間が12時からを予定しております。
また、開店セールを行います。期間は4/1~5/31までとなります。
古書のみ2割引にて販売致します。ご来店お待ちしております。
なお、現在地での事務所としての営業は3/14までを予定しております。
3/14までは納品、発注等は今現在の住所、連絡先へお願い致します。
3/15からは電話番号、FAX番号も変更致しますので、ご注意くださいませ。
新店舗連絡先
〒901-2215 沖縄県宜野湾市真栄原3-8-3 大光ビルⅢ-203
TEL:098-943-7991 FAX :098-943-7274
店舗営業時間 12:00~19:00
定休日:日曜・祝祭日


Posted by 沖縄本といえば榕樹書林 at
18:06
│Comments(0)
2024年02月27日
弊社刊 故真栄平房昭著『琉球海域史論』、第41回東恩納寛淳賞受賞
長年琉球史研究の発展に貢献してきた、故真栄平房昭氏に哀悼の意を捧げるとともに、
東恩納寛淳賞の受賞を喜ばしく思います。
『琉球海域史論』は病床に臥した真栄平氏を励ますため、2020年に発刊した論文集です。
21年には伊波普猷賞を受賞しております。
贈呈式は3月13日18時30分より、那覇市泉崎の琉球新報ホールにて。


琉球新報デジタル版URL
https://ryukyushimpo.jp/?s=%E7%9C%9F%E6%A0%84%E5%B9%B3%E6%88%BF%E6%98%AD
弊社ネットURL
https://gajumarubook.jp/?mode=srh&cid=&keyword=%CE%B0%B5%E5%B3%A4%B0%E8%BB%CB%CF%C0
東恩納寛淳賞の受賞を喜ばしく思います。
『琉球海域史論』は病床に臥した真栄平氏を励ますため、2020年に発刊した論文集です。
21年には伊波普猷賞を受賞しております。
贈呈式は3月13日18時30分より、那覇市泉崎の琉球新報ホールにて。


琉球新報デジタル版URL
https://ryukyushimpo.jp/?s=%E7%9C%9F%E6%A0%84%E5%B9%B3%E6%88%BF%E6%98%AD
弊社ネットURL
https://gajumarubook.jp/?mode=srh&cid=&keyword=%CE%B0%B5%E5%B3%A4%B0%E8%BB%CB%CF%C0
2023年12月29日
*年末年始休業のお知らせ*

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、年末年始の休業を下記の通りご案内させていただきます。
休業期間 2023年12月30日(土) ~ 2023年1月3日(水)
上記期間は、ネットショップの対応業務も休止致します。
尚、ご注文およびメールでのお問い合わせは通常通り受け付けておりますが、
発送および返信は1月4日(木)以降となります。
何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら、年末年始の休業を下記の通りご案内させていただきます。
休業期間 2023年12月30日(土) ~ 2023年1月3日(水)
上記期間は、ネットショップの対応業務も休止致します。
尚、ご注文およびメールでのお問い合わせは通常通り受け付けておりますが、
発送および返信は1月4日(木)以降となります。
何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
Posted by 沖縄本といえば榕樹書林 at
18:15
│Comments(0)
2023年12月28日
弊社刊 茂木仁史・古波蔵ひろみ著『首里城の舞台と踊衣裳』令和五年度本田安次賞受賞
共著者のうちの一人、茂木仁史先生が令和五年度本田安次賞を受賞いたしました。
一連の研究から首里城の舞台と芸能の関係等を明らかにし、それを評価され受賞いたしました。
授賞内容:
著書『首里城の舞台と踊衣装』
(榕樹書林(「踊衣装」の章は古波蔵ひろみ著)、2023年2月)
及び、
論文「首里城の「御城舞台」と「火花」」
(『藝能』第29号、2023年3月

沖縄タイムス掲載2023.12.28、琉球新報掲載2023.12.27
民俗芸能学会HP
https://www.minzokugeino.com/
弊社ネットショップ
https://gajumarubook.jp/?mode=srh&cid=&keyword=%CC%D0%CC%DA%BF%CE%BB%CB
一連の研究から首里城の舞台と芸能の関係等を明らかにし、それを評価され受賞いたしました。
授賞内容:
著書『首里城の舞台と踊衣装』
(榕樹書林(「踊衣装」の章は古波蔵ひろみ著)、2023年2月)
及び、
論文「首里城の「御城舞台」と「火花」」
(『藝能』第29号、2023年3月

沖縄タイムス掲載2023.12.28、琉球新報掲載2023.12.27
民俗芸能学会HP
https://www.minzokugeino.com/
弊社ネットショップ
https://gajumarubook.jp/?mode=srh&cid=&keyword=%CC%D0%CC%DA%BF%CE%BB%CB
2023年12月11日
2023年12月07日
がじゅまるブックス19 『原郷のニライカナイへ』 本日より販売開始!
〈久高島の民俗グラフィティ〉 がじゅまるブックス⑲
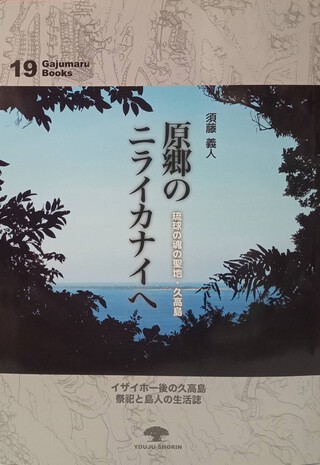
須藤義人著(沖縄大学教授)
十二年に一度の琉球王国成立に関わる祭祀としてのイザイホーは、一九七八年をもって中止となり、その後も再開には至っていない。祭祀をになう神人のにない手が過疎に伴って不在となったことによるものだが、イザイホーをめぐる議論は今もなお熱く続いている。それはそれとしても、イザイホーが中止になったとはいえ、久高島には今も多くの人が住み、それ以外の祭祀を黙々と受けつぎ、島の発展の為に力を尽して生きている。
本書は最後のイザイホーの後、島の人々がいかに島の生活を祭祀と共に生きてきたのかを淡々と記録するとともにその聖なる領域との魂の交感をうたい上げ、島の未来への希望を記した映像民俗学のマニフェストである。
写真六五点は島の人々の祭祀と生活を余すところなくとらえ、久高島がなにゆえに「聖地」なのかを読者に提示してくれるであろう。
A5判、並製、116頁、写真図版65点, 定価1,320円(本体1,200円+税)
~目次~
はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
1 海と島の思想 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
2 里海と里森の世界観 ・・・・・・・・・・・・7
3 久高島の宇宙観 ・・・・・・・・・・・・・・・14
4 御嶽信仰―神界と人界の境界 ・・・・22
5 水神信仰・農耕儀礼 ・・・・・・・・・・・・32
6 来訪神信仰 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
7 他界信仰 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
8 オナリ神とエケリ神 ・・・・・・・・・・・・・ 60
9 生きるよすがとしての生態智 ・・・・・・・74
10 霊性のコモンズと死生観 ・・・・・・・・・ 91
おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107
~著者プロフィール~
一九七六年横浜に生る
早稲田大学社会科学部卒
沖縄県立芸術大学大学院を経て
現在沖縄大学教授
宗教哲学、映像民俗学
著書、映像作品多数
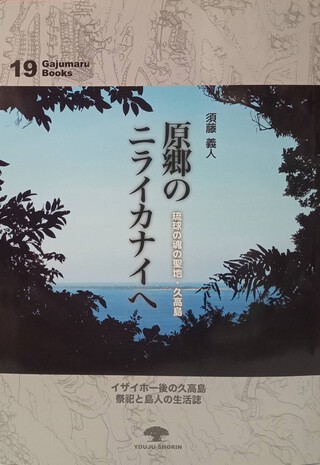
須藤義人著(沖縄大学教授)
十二年に一度の琉球王国成立に関わる祭祀としてのイザイホーは、一九七八年をもって中止となり、その後も再開には至っていない。祭祀をになう神人のにない手が過疎に伴って不在となったことによるものだが、イザイホーをめぐる議論は今もなお熱く続いている。それはそれとしても、イザイホーが中止になったとはいえ、久高島には今も多くの人が住み、それ以外の祭祀を黙々と受けつぎ、島の発展の為に力を尽して生きている。
本書は最後のイザイホーの後、島の人々がいかに島の生活を祭祀と共に生きてきたのかを淡々と記録するとともにその聖なる領域との魂の交感をうたい上げ、島の未来への希望を記した映像民俗学のマニフェストである。
写真六五点は島の人々の祭祀と生活を余すところなくとらえ、久高島がなにゆえに「聖地」なのかを読者に提示してくれるであろう。
A5判、並製、116頁、写真図版65点, 定価1,320円(本体1,200円+税)
~目次~
はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
1 海と島の思想 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
2 里海と里森の世界観 ・・・・・・・・・・・・7
3 久高島の宇宙観 ・・・・・・・・・・・・・・・14
4 御嶽信仰―神界と人界の境界 ・・・・22
5 水神信仰・農耕儀礼 ・・・・・・・・・・・・32
6 来訪神信仰 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
7 他界信仰 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
8 オナリ神とエケリ神 ・・・・・・・・・・・・・ 60
9 生きるよすがとしての生態智 ・・・・・・・74
10 霊性のコモンズと死生観 ・・・・・・・・・ 91
おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107
~著者プロフィール~
一九七六年横浜に生る
早稲田大学社会科学部卒
沖縄県立芸術大学大学院を経て
現在沖縄大学教授
宗教哲学、映像民俗学
著書、映像作品多数
2023年12月07日
観宝堂編『沖縄の古陶』『八重山の古陶』『琉球王朝の書画』取り扱い開始!
琉球古美術の第一人者、観宝堂吉戸氏によって編纂された非売品3点を弊社より一般販売する事に致しました。
また、この3点以外にも琉球・沖縄の美術・工芸品に関する図録(古書扱い)などが多数入荷しております。
この機会にぜひご検討くださいませ。
『沖縄の古陶』

24×25.2、並製、180頁、カラー図版269点、税込4950円
沖縄の古陶は一部の熱狂的なファンに支えられ高い評価を得てきたが、不明な事が多く、どこの誰のものなのか、いつの頃のものなのか、錯綜した状況が長く続いてきた。
この状況に一石を投じたのが一九七一年、那覇に店を構えた「古美術観宝堂」であった。
沖縄で初めての本格的な古美術店として、とりわけ「やちむん」の評価について他の追随を許さない確かな「眼」をもって新しい市場形成を主導してきたのである。
本書は観宝堂主人、吉戸直氏が収集した琉球沖縄の古陶を、その産地、年代等を明示し、やちむんを愛する人々に「眼」の基準を提供する。写真も古美術品撮影のプロによって美しく、かつわかりやすいものになっている。
本書は沖縄古陶収集の最も信頼できるガイドブックとして高い評価を得ていたが、厳密に非売品として扱われてきたものを、吉戸氏の病気に伴い閉店するにあたって広く一般に提供することとなったものである。
市販部数90部となる。尚、本書は並製版となる。上製凾入の特装本については古書扱いで販売致します。
目次(抄)
沖縄古窯地図
図版 焼く/造る/彩る/描く
巧み/食と酒/祈る
焼きもの雑考―大嶺実清
沖縄の古陶 細部拝見
沖縄の古陶年表
参考文献
『八重山の古陶』
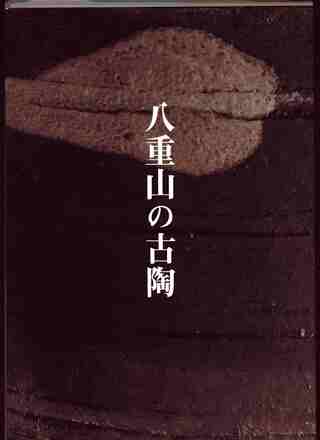
A4判、並装 160頁、オールカラー写真図版109点 税込3,850円
八重山の古陶とは何か、このことを各美術館・博物館の協力をもとに古美術観宝堂・吉戸直氏が大系的に八重山古陶をとらえなおし、図版を集大成し、かつ八重山古陶を再評価したのが本書である。ここに八重山の古陶器は明確な姿をもって琉球古美術の世界にたちあらわれたといっていいであろう。いわば独自の美意識のもとで分立を宣言したのである。
この図録は観宝堂・吉戸氏の長年にわたる古美術を見る眼の凝縮された結実というべきものである。
非売品であったが為にごく一部の人しか眼にすることのなかった図版が今ここに開放されたのだ。
〈本書協力施設〉
沖縄県立博物館/石垣市立博物館
諸見民芸館/那覇市立壺屋焼物博物館
早稲田大学會津八一記念博物館
八重山古陶研究会/丹尾安典教授
贈
八重山古陶名品撰
八重山古陶の器底
八重山古陶年表
『未公開作品による琉球王朝の書画』

A4判、並製、オールカラー、150頁、税込3,850円
琉球王朝の絵画13点、書57点
琉球の書画は、日本と中国の影響を受けながらも独自の美を求めて展開された。それは中国からの冊封使の来琉、あるいは江戸へのいわゆる「江戸立ち」を通して独自の位置を形成してきたといえよう。しかしいわゆる「琉球処分」や過酷な沖縄戦による文化財破壊等によって、その全貌は今もって定かではない。
本書は琉球古美術の第一人者として誰もが認めている観宝堂吉戸氏の蓄積を全七〇点の図版、それも各品々に押されている印も全て実物大で掲載し、真贋判定にも役立たせる様に配慮している。平成四年に刊行されて以来、厳密に非売品管理をしてきた為に琉球古美術を扱う業者のいわば「虎の巻」として引っ張りだこになっていた図録が遂に一般販売されることとなったのは、同好の士にとっては待ちかねていた大きなチャンスかもしれない。
編集協力:池宮正治・田名真之・津波古聡・盛島高行
ご購入は下記URLより。
https://gajumarubook.jp/?mode=cate&cbid=1392317&csid=0
また、この3点以外にも琉球・沖縄の美術・工芸品に関する図録(古書扱い)などが多数入荷しております。
この機会にぜひご検討くださいませ。
『沖縄の古陶』

24×25.2、並製、180頁、カラー図版269点、税込4950円
沖縄の古陶は一部の熱狂的なファンに支えられ高い評価を得てきたが、不明な事が多く、どこの誰のものなのか、いつの頃のものなのか、錯綜した状況が長く続いてきた。
この状況に一石を投じたのが一九七一年、那覇に店を構えた「古美術観宝堂」であった。
沖縄で初めての本格的な古美術店として、とりわけ「やちむん」の評価について他の追随を許さない確かな「眼」をもって新しい市場形成を主導してきたのである。
本書は観宝堂主人、吉戸直氏が収集した琉球沖縄の古陶を、その産地、年代等を明示し、やちむんを愛する人々に「眼」の基準を提供する。写真も古美術品撮影のプロによって美しく、かつわかりやすいものになっている。
本書は沖縄古陶収集の最も信頼できるガイドブックとして高い評価を得ていたが、厳密に非売品として扱われてきたものを、吉戸氏の病気に伴い閉店するにあたって広く一般に提供することとなったものである。
市販部数90部となる。尚、本書は並製版となる。上製凾入の特装本については古書扱いで販売致します。
目次(抄)
沖縄古窯地図
図版 焼く/造る/彩る/描く
巧み/食と酒/祈る
焼きもの雑考―大嶺実清
沖縄の古陶 細部拝見
沖縄の古陶年表
参考文献
『八重山の古陶』
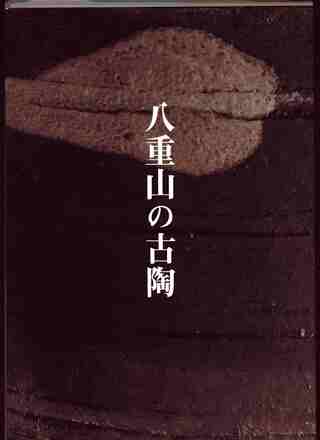
A4判、並装 160頁、オールカラー写真図版109点 税込3,850円
八重山の古陶とは何か、このことを各美術館・博物館の協力をもとに古美術観宝堂・吉戸直氏が大系的に八重山古陶をとらえなおし、図版を集大成し、かつ八重山古陶を再評価したのが本書である。ここに八重山の古陶器は明確な姿をもって琉球古美術の世界にたちあらわれたといっていいであろう。いわば独自の美意識のもとで分立を宣言したのである。
この図録は観宝堂・吉戸氏の長年にわたる古美術を見る眼の凝縮された結実というべきものである。
非売品であったが為にごく一部の人しか眼にすることのなかった図版が今ここに開放されたのだ。
〈本書協力施設〉
沖縄県立博物館/石垣市立博物館
諸見民芸館/那覇市立壺屋焼物博物館
早稲田大学會津八一記念博物館
八重山古陶研究会/丹尾安典教授
贈
八重山古陶名品撰
八重山古陶の器底
八重山古陶年表
『未公開作品による琉球王朝の書画』

A4判、並製、オールカラー、150頁、税込3,850円
琉球王朝の絵画13点、書57点
琉球の書画は、日本と中国の影響を受けながらも独自の美を求めて展開された。それは中国からの冊封使の来琉、あるいは江戸へのいわゆる「江戸立ち」を通して独自の位置を形成してきたといえよう。しかしいわゆる「琉球処分」や過酷な沖縄戦による文化財破壊等によって、その全貌は今もって定かではない。
本書は琉球古美術の第一人者として誰もが認めている観宝堂吉戸氏の蓄積を全七〇点の図版、それも各品々に押されている印も全て実物大で掲載し、真贋判定にも役立たせる様に配慮している。平成四年に刊行されて以来、厳密に非売品管理をしてきた為に琉球古美術を扱う業者のいわば「虎の巻」として引っ張りだこになっていた図録が遂に一般販売されることとなったのは、同好の士にとっては待ちかねていた大きなチャンスかもしれない。
編集協力:池宮正治・田名真之・津波古聡・盛島高行
ご購入は下記URLより。
https://gajumarubook.jp/?mode=cate&cbid=1392317&csid=0
2023年12月06日
2023年11月16日
12/10(日)15時よりジュンク堂書店那覇店にて『原郷のニライカナイへ』発売記念トークイベント開催のお知らせ
12/10(日)15時より『死を想いつつ、生を紡ぐこと』と題しましたトークイベントを開催致します。
対談者は、須藤義人 (著者・沖縄大学人文学部教授)×大下大圓 (飛騨千光寺長老・沖縄大学客員教授)です。
このトークイベントは12月9日発売予定の須藤義人著『原郷のニライカナイへ 琉球の魂の聖地・久高島』の刊行を記念しております。
お近くへお越しの際は、お立ち寄りいただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
【日時】
2023年12月10日日曜日 15:00~(1時間程度)
【場所】
ジュンク堂書店那覇店地下1階イベント会場
※ご参加は無料でございます。
イベントに関するお問い合わせは、小社(TEL:098-893-4076)もしくはジュンク堂書店那覇店(TEL:098-860-7175)まで。

対談者は、須藤義人 (著者・沖縄大学人文学部教授)×大下大圓 (飛騨千光寺長老・沖縄大学客員教授)です。
このトークイベントは12月9日発売予定の須藤義人著『原郷のニライカナイへ 琉球の魂の聖地・久高島』の刊行を記念しております。
お近くへお越しの際は、お立ち寄りいただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
【日時】
2023年12月10日日曜日 15:00~(1時間程度)
【場所】
ジュンク堂書店那覇店地下1階イベント会場
※ご参加は無料でございます。
イベントに関するお問い合わせは、小社(TEL:098-893-4076)もしくはジュンク堂書店那覇店(TEL:098-860-7175)まで。